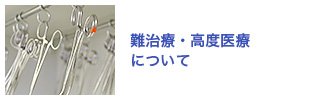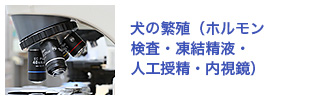最近のブログ
カレンダー
最近のエントリー
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
猫の末端肥大症
16年01月17日
猫の末端肥大症(高ソマトトロピン症)は、下垂体前葉に生じた成長ホルモン産生腫瘍が原因になることが最も一般的です。以前は稀な疾患であると考えられていました。しかし、現在まで診断されていなかったためによるものか、疾患として増えてきたかは明らかではありませんが、最近の研究によれば高ソマトトロピン血症は糖尿病の猫の約25%に存在すると推定されています。
症状としては、多飲、多尿、多食、体重増加、跛行、神経症状、蹠行姿勢、趾の腫大、幅広い顔面、歯間腔の拡大、顎前突などが挙げられます。多くの症状は併発する糖尿病に関連するものですが、身体的な変化は末端肥大症の特徴的な変化であると言えます。しかし、こういった身体的な変化はゆっくりと起こるため、普段一緒に過ごされている飼い主様には分かりづらいことが多いです。また、通常血糖値の管理が困難な糖尿病患者には、体重減少が起こりますが、末端肥大症に起因する糖尿病の場合、血糖値の管理が不十分でも体重の増加が認められるという点で、通常の糖尿病との鑑別が可能です。しかし、稀ではありますが、糖尿病でない末端肥大症の報告例も存在し、また特徴的な身体所見の変化をほとんど認めない末端肥大症も存在するなど、診断が困難な場合もあります。
現在のところ、末端肥大症を確定診断するためのゴールド・スタンダードとなる検査法は存在しません。そのため、ほとんどの症例において、臨床徴候、IGF-1濃度の測定、画像診断を組み合わせて診断を行っていきます。
治療には、 放射線療法、下垂体切除術、内科療法などが行われます。放射線療法に対する反応は様々で、成功症例では血糖値のコントロールの改善あるいは糖尿病の寛解が得られることもありますが、反応に乏しく、効果が持続しない場合もあります。下垂体切除術はヒト医療においては第一選択となり、猫においても報告例が存在しますが、極めて少数で、また生涯に渡るホルモンの補充が必要となります。内科療法は理論的には有効であると考えられますが、現在のところ獣医文献での報告は少なく、少数の症例報告に限られるため更なる研究が必要であると考えられています。
犬の甲状腺摘出手術です。
16年01月17日