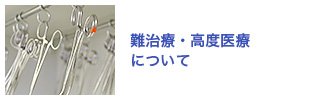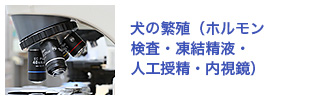カレンダー
最近のエントリー
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
副腎皮質機能低下症(アジソン病)
13年12月25日
副腎とは腎臓のそばにある、主にホルモンを産生する内分泌器官です。副腎皮質機能低下症とは副腎でのミネラルコルチコイドとグルココルチコイドが共に分泌不全となる病気で、それに伴う全身的な症状が現れます。元気消失、食欲不振、震えなどがみられますが、多くは下痢や嘔吐などの消化器症状や低血糖に伴う症状で発見されることが多いです。他の内分泌疾患の多くと異なりこの病気は若~中齢での発症が多く、身体検査では脱水、徐脈、体重減少などがみられます。
検査では高カリウム血症、低ナトリウム血症(Na/K=27以下)、低血糖、高窒素血症や腹部超音波検査での小さな副腎の描出、そしてACTH刺激試験での異常低値が確定診断となります。
急性の副腎機能不全(アジソンクリーゼ)の場合は緊急性があり、ショックに陥っているために循環血液量の回復のための点滴、高カリウムの補正、低血糖の是正、そして速効性の水溶性グルココルチコイドの投与を行います。通常は2.3日くらいで改善がみられ、維持療法へとうつります。ミネラルコルチコイド製剤であるフロリネフ(酢酸フルドロコルチゾン)とプレドニゾロンの内服投与法では電解質をみながら投与量を調節します。最近ではDOCP(デソキシコルチコステロンピバレート)を25日毎に筋肉注射とプレドニゾロンの内服投与することで副作用も少なく良好にコントロールできると感じております。
この病気の予後は良好で、積極的に治療していくことで本来の寿命を全うできるといわれています。
T.S.
DOCP製剤

猫のアセトアミノフェン中毒
13年12月18日
この時期飼い主様も風邪を引かれている方が多いのではないでしょうか?人で使用される市販の風邪薬にはアセトアミノフェンという成分が含まれているものが多く、この物質は猫にとっては非常に危険なものです。猫には薬を代謝し、排泄する機能の一つである「グルクロン酸抱合能」というものが乏しく、体内に入ったアセトアミノフェンを上手く排泄することが出来ません。よって、少量のアセトアミノフェンを摂取しても中毒症状が起きてしまう可能性があります。3.5kgの猫に162.5mgのアセトアミノフェンに対して中毒症状を示したという例もあります。主な症状は呼吸困難、顔面浮腫、低体温、嘔吐がみられ、重症になると衰弱、昏睡し、死に至ります。
市販の薬には1錠(1包)40~500mgのアセトアミノフェンが含まれています。(詳しくは薬の取り扱い説明書等を参考にしてください。) つまり、人にとっては適切な1回量であっても猫にとっては致死量になってしまうということです。
緊急の処置として気道確保、喚気、酸素吸入、輸液、痙攣のコントロール、原因物質の除去等が挙げられます。アセトアミノフェンは摂取されると急速に体内に吸収され、30~60分以内に血中濃度が最大になると言われており、摂取後は迅速な処置が必要とされます。
もし、お家で猫が間違って薬を飲んでしまった場合はすぐにお近くの動物病院に連絡しましょう。また、薬の管理は猫が届かないような場所で、床等にこぼさないようにお気をつけください。
D.T
消化管間質腫瘍(gastrointestinal stromal tumor:GIST)
13年12月11日
従来、犬の消化管粘膜下に発生する間葉系腫瘍の大部分は、平滑筋腫および平滑筋肉腫と考えられてきました。しかし、2003年にこれらの中に消化管間質腫瘍(GIST)が含まれていると報告され、獣医領域に新しい腫瘍の概念が加わりました。
GISTは大腸、特に盲腸に発生が多いとされています。(これに対して平滑筋腫は胃に好発するといわれています。)腹腔内の巨大腫瘤として発見されることが多いのですが、これは粘膜下腫瘤であるためサイズが大きくなるまで臨床症状を示さないためではないかと考えられています。
GISTは、外見上は平滑筋腫や平滑筋肉腫と類似しており、超音波検査やCT検査では鑑別が難しく、多くの場合は悪性であることを想定して外科的切除が実施されます。
またGISTは、c-kitと呼ばれる遺伝子に変異が認められるという特徴を有しており、不完全切除や再発症例ならびに転移症例では内科療法として分子標的薬の投与が考慮されます。ヒトでは分子標的薬であるメシル酸イマチニブが再発性ならびに転移性GISTの第一選択薬とされていて、犬においても効果が認められたという報告もあります。
H.B.
犬趾間皮膚炎
13年12月04日
肢先、つまり人でいう指や指の間に炎症が起こり、犬が舐めてしまっての脱毛、腫脹、発赤、疼痛を伴う皮膚炎は比較的よく遭遇する疾患です。原因は、解剖学的な問題、アレルギー、感染、代謝疾患、免疫的な問題、異物、創傷、環境因子など多岐に渡ります。残念なことに、個々の症例において、原因を特定する診断的な身体所見はありません。診断として、細胞診、皮膚スクラッチ検査、バイオプシー検査が有用になることがあります。また原因は1つとは限らず、根本的な原因に感染症が重なって症状がひどくなっていることもあります。アカラス症は、若齢犬や老齢犬に多い原因の一つです。また趾間は、異物が他の場所と異なり入り込みやすく、異物反応の結果皮膚病が落ち着かないことがあります。他にも自らの肢をなめ続けることによって、ケラチンが皮膚の中に押し込み、体が異物と認識することや毛包が破裂し体が毛根を異物と認識してしまい過剰に異物反応が出てしまうことがあります。異物反応が出ている場合は、その部位を切除することで改善が見られます。逆に切除をしないと症状が落ち着かないことが多いです。
二次的な感染症は、抗生剤や、抗真菌剤で落ち着かせることが出来ますが、根本がアレルギーが原因である場合、残念ながら繰り返すことの多い疾患ではあります。
自分で咬んでしまう結果、皮膚が損傷を受け皮膚バリア機能が低下し感染症が悪化をすることがあります。
治療は、まず感染症があるなら感染症の治療を始めます。 環境因子の除去のために足先だけ定期的にシャンプーすると改善が認められることもあります。 また異物反応が考えられるなら原因除去、アレルギーが疑われるならそれに対する治療、免疫的な疾患の場合は免疫抑制剤治療など原因や症状によって選択する治療は異なってきます。
趾間皮膚炎は飼い主様にとってもワンちゃんにとってもとてもストレスのかかる病気です。
原因は1回では分からないこともありますが、経過とともに改善が見込める病気でもあると思います
ワンちゃんのストレスを軽減できるお手伝いが出来れば・・と思います M.N