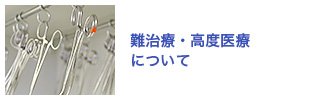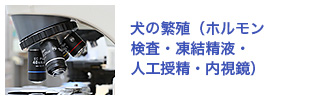カレンダー
最近のエントリー
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
精巣の感染症
17年04月23日
ワンちゃんの繁殖障害にはたくさん原因がありますが、そのなかで感染症によるものがあります。有名なものにはブルセラ病がありますが、そのほかにもMycoplasmaなどが挙げられます。全身感染を起こしていれば発熱などで気がつくのですが、多くは慢性、局所的な感染で若干の不快感程度のものや症状があきらかに現れないものがほとんどです。精巣に感染症がある場合、精液中に炎症性細胞や形態異常の精子が多く現れたり精子数が減少していたりします。しかし射精精液中に細菌が現れることはほとんどなく、確定診断には穿刺吸引した検体の培養などが挙げられますが、なかなか実施しにくいところです。その場合試験的に抗生剤の投薬を行い、反応を見ています。不妊症からの回復の予後は必ずしもよくないです。不妊が続いた場合は最終的に摘出してあげるのがいいかもしれません。 K.Y
マール眼発育異常
17年04月16日
マール眼発育異常はマールカラーやダッフルカラーの犬種に見られる、不完全常染色体劣性遺伝が推測される眼の以上です。この遺伝子を持つ好発犬種(オーストラリアンシェパード、コリー等)の片眼あるいは両眼にみられ、またこの疾患を持つ犬では聴覚障害も知られています。マール遺伝子を持つ犬では毛色が薄い、つまりメラニン細胞が少ないためいわゆるマールカラー・ダッフルカラーといった毛色になります。メラニン細胞はもともと発生の過程で視神経堤細胞から分化するのですが、視神経堤細胞からはメラニン細胞以外に眼では角膜、強膜、ぶどう膜、外眼筋になり、耳では内耳の形成にかかわっていきます。しかしマール遺伝子を持つ犬ではそのもととなるメラニン細胞が少ないため形成に必要な細胞が足りなく、このような異常が出てしまいます。
症状として、小眼球、異常な形の小角膜、角膜実質への沈着物、瞳孔変形を伴った虹彩異色や虹彩低形成、偽多瞳孔、隅角異常などの多発性眼異常がみられます。白内障は小眼球とコロボーマをもった犬の60%に起こることが知られています。赤道部のブドウ腫、コロボーマ、脈絡膜低形成や網膜剥離は、網膜色素上の発育異常が原因です。治療法はなく、基本的に同色同士の繁殖をできるだけしないようにということになります。
S.A
インターフェロンを用いたがん治療
17年04月09日
インターフェロン療法はがんに対する免疫療法のひとつです。がんの治療では、現在広く行われている外科療法、化学療法、放射線療法に続き、免疫療法が第4の治療法として期待されています。
生体にはNK細胞やキラーT細胞、マクロファージ、ヘルパーT細胞などといった腫瘍に対する免疫学的監視機構がもともと備わっています。腫瘍罹患犬は健常犬と比較するとこれらの細胞が減少し、逆に抗腫瘍免疫を抑制する制御性T細胞が増加しています。インターフェロンの主な抗腫瘍効果には、全身・腫瘍組織中の免疫担当細胞を刺激・活性化させる間接作用と、細胞死(アポトーシス)の誘導促進や細胞増殖抑制といった直接作用があります。肥満細胞腫、悪性黒色腫、上皮向性リンパ腫、移行上皮癌などの悪性腫瘍に対してインターフェロンを用いた症例が近年報告されています。
当院においても腫瘍症例に対する治療オプションのひとつにインターフェロン療法を採用しております。ご検討の飼い主様はその詳細についてぜひ獣医師にご相談ください。
H.B.
椎間板ヘルニアにおける幹細胞療法(ペットの再生医療)
17年04月07日
「おはよう朝日です」に獣医再生医療学会会長の岸上先生が出演し、ペットの再生医療が紹介されてました。椎間板ヘルニアに幹細胞療法を行うことにより神経の再生は促され、歩けるようになる症例は当院でもたくさんいます。その他にも、骨折・骨癒合不全、脊髄損傷、炎症性関節炎、腎不全、肝硬変、自己免疫性疾患、膵炎などの治療に使用し、良い経過が得られています。多くの病気に効果が期待され人医療においても治療が行われています。
また、このたび日本獣医再生医療学会と日本獣医再生・細胞療法学会は、かねてより検討しておりましたペットの犬や猫への再生医療などについて、獣医師が治療を実施する際のガイドラインをまとめペットやご家族の皆様が安心して治療をうけていただけるような指針を発表いたしました。治療法がないとあきらめる前にぜひご相談してみてください。
S.S
熱中症
17年04月02日
依然朝晩は肌寒い日がありますが、日中は大分暑い日も多くなってきました。今からの季節、気をつけないといけなくなるのは熱中症です。
熱中症は、高温多湿環境下による高体温や脱水によって引き起こされる全身性の疾患です。動物の熱中症は、①高温多湿環境下への長時間の暴露、②熱放散能の低下、③過度の運動、などが原因となります。特に②の熱放散能の低下の原因としては、短頭種、肥満、大型犬などの身体的特徴や、心疾患、呼吸器疾患などの病的状態などがあります。
熱中症の症状は、粘膜のうっ血および充血、頻脈、パンティングなどがあり、より重篤化すると虚脱、運動失調、嘔吐、下痢、流涎、振戦、意識消失、発作などが認められるようになります。
診断は、臨床症状と直腸温が40.5℃以上であれば確定的ですが、各臓器の障害程度の把握のために血液検査を実施します。多臓器不全に陥っている場合や、播種性血管内凝固(DIC)を引き起こしている場合には、適切な治療を行っても死亡率は高いです。
治療は、まずは身体を冷やすことが基本になります。一番簡単で効果的な方法は、常温の水道水で濡らして扇風機で送風し、気化熱を利用して冷却する方法です。冷水や氷、アイスパックなどを用いて急速に冷却すると、体表の血管が収縮し、温度の高い血液が体の内部の各臓器へ循環して、熱が体表から放散されにくくなります。その結果、深部体温が低下せず、高体温による各臓器への障害が促進され、逆効果となってしまいます。よって、熱中症を疑う場合は、まずは体温を測定してもらい。40.5℃以下で意識がはっきりしている場合には、風通しの良い場所や冷房の効いた場所に移して水を十分に飲ませて頂きます。体温が40.5℃以上や意識レベルが低下している場合には、水道水で体全体を濡らすか、水で濡らしたタオルで全身をつつみ、扇風機などで風を当てて冷却してもらい、病院に移動する最中も、車内の冷房や車の窓からの風を利用して冷却してもらうと良いです。
熱中症が原因で動物病院を緊急で受診する犬の死亡率は50%で、死亡例の多くは受診後24時間以内に亡くなってしまいます。熱中症を起こした動物を救命するためには、より早期から冷却処置を行い正常体温に回復させ、各臓器へのダメージを最小限に留めることが重要です。しかしながら、前述の通り、重症例は適切な治療を行っても救命できないことがあります。近年、地球温暖化の影響で平均気温が上昇しており、夜間での熱中症の報告例もあります。段々と暑くなっていく今からの季節、愛犬たちの温度管理には十分に注意してください。
T.H.