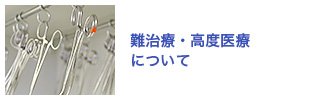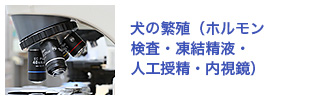カレンダー
最近のエントリー
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
椎間板脊椎炎
14年01月26日
椎間板脊椎炎は椎間板の炎症や感染および隣接する椎骨終板や椎体の骨髄炎と定義されます。最も一般的な原因は細菌の椎間腔への血行性散布による発症であり、引き続き隣接する椎骨に炎症は波及します。
症状は、感染による沈うつ、食欲低下、発熱、体重減少などの全身症状から、硬直や歩行困難など様々です。炎症性組織の増殖・肥厚や髄膜を介した炎症の拡大、および椎体の病的骨折や椎間板突出の併発など病変の部位や重篤度によっては運動失調、不全麻痺、麻痺が引き起こされます。
診断は病歴や身体検査および神経学的検査、血液検査に基づいて行われます。X線検査では、椎体終板の溶解や隣接椎体の骨溶解、椎体間のブリッジ形成や狭小化などが認められます。CT検査およびMRI検査も診断に利用されます。原因細菌の特定のために血液や尿の培養が実施される場合もありますが、陽性結果が得られるのは40~75%ともいわれています。
治療は抗生物質治療が一般的ですが、過去の文献では2~4か月の継続的治療が必要であったという報告もあります。椎体の病的骨折や椎間板突出が併発している症例では外科手術が必要な場合もあります。神経学的徴候が軽度で、多発性病変や椎体骨折、不安定化や脱臼がみられない限り、一般的に予後は良好です。
H.B.
開口、閉口障害
14年01月19日
口を開閉する運動は、動物にとって非常に頻繁に行われる運動の一つです。犬や猫は、主に肉を噛み切る運動である上下の一軸性の運動が主で、兎や牛のような臼歯で草をすり潰す運動のである側運動や、前後方向への運動はほとんど認められません。 顎の運動は骨や関節の構造や、筋肉、神経、正常な噛み合わせで正常に行われます。ほとんどの哺乳動物の咀嚼に関わる筋肉は、顎二腹という筋肉以外が口を閉じる運動をし、かつ三叉神経という一つの神経の支配を受けます。また犬や猫の噛み合わせが悪いと、正常に口を閉じる事が出来ません。いわゆる不正咬合には上下顎の長さや、左右の対称に不正がある骨格性不正咬合と歯の問題である歯性不正咬合があります。
顎運動障害の原因としては、成長過程で関節や骨に問題が生じる発生性や、口腔内や関節、筋肉に炎症が生じる炎症性、外傷性、腫瘍性、筋肉に問題が起こる筋性、三叉神経や、口を開く時に必要な筋肉の神経を支配している顔面神経の異常で問題が起こる神経性や不正咬合でおこります。上記のように様々な原因で口が開かなかったり、閉じなかったりします。特に三叉神経がこの顎の運動に大きく関わるので、三叉神経の麻痺があれば、口が閉じれなくなり、逆に筋肉の炎症が起こると筋肉の疼痛と肥厚で、口が開かなくなるというのは、関わっている神経や筋肉の解剖を考えるととても興味深く感じます。
診断には、レントゲンやCT、麻酔下での運動性の確認などが必要になります。顎の運動の障害は、物を食べるという大切な運動の妨げになります。口を触られるのを極端に嫌がる、欠伸をしにくそう、など気になる事がありましたらご相談下さい。
M.N.
播種性血管内凝固症候群(DIC)
14年01月12日
播種性血管内凝固(Disseminated Intravascular Coagulation、以下DIC)は、様々な基礎疾患によって、全身の主として細小血管内に多発的にフィブリン形成(=血栓形成)が生じる病態です。DICが発生した場合には、血栓形成による臓器障害が大きな問題となると共に、血小板や凝固因子の消費および線溶活性化によって出血傾向となることも大きな問題となります。DICが発生している場合や発生しつつある状態においては、命に関わる状況に陥る可能性を考慮しなければなりません。
イヌにおいてのDICの発生を考慮すべき疾患としては、悪性腫瘍が代表的で、血管肉腫、乳腺癌、組織球肉腫、肝細胞癌、胆管癌、リンパ腫、肥満細胞腫、急性白血病などで多く認められます。その他、非腫瘍性疾患でDICが起こり易いものとして、急性膵炎、免疫介在性溶血性貧血、子宮蓄膿症、重篤な腸炎、敗血症、バベシア症、熱中症、胃拡張捻転症候群、交通事故、手術などが挙げられます。
DICの診断においては、血小板数の他、フィブリノゲン(Fib)、プロトロンビン時間(PT)、活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)、フィブリン/フィブリノゲン分解産物(FDP)、アンチトロンビン(AT)、D-dimerなどが測定されます。教科書的なDICの基準としては、基礎疾患の存在に加え、血液凝固線溶系検査6項目(血小板数、Fib、FDP、PT、APTT、AT)のうち4項目以上の異常値が挙げられていますが、検査項目が多く早期のDICを検出するためには基準が厳しすぎるという事から、昨今においてはDICを発生しうる基礎疾患があり、①血小板数の減少、②FDP値の上昇、③PTまたはAPTTの基準値の25%以上の延長、といった3項目のうち、2項目を満たす場合に「Suspected DIC」、3項目すべて満たす場合にDICとする基準が臨床的に有用であるとされています。この「Suspected DIC」の状況は、DICに進む途中の段階(=Pre DIC)に相当するものと考えられ、臨床的に重要な段階であるといえます。
DICは二次的な症候群であって、その背景にはDICを引き起こす基礎疾患が存在します。つまりなるべく早期に診断し、Pre DICおよびそれに入る前の段階での基礎疾患に対する強力で有効な治療を開始することがDICを治療することにつながります。DICが発生した場合は、抗血栓治療として低分子量ヘパリン、抗血小板療法として超低用量アスピリン療法、凝固因子や血小板を補充する目的として新鮮全血輸血または新鮮血漿輸血などが考慮されます。 T.H.
フェレットのインシュリノーマ
14年01月05日
インシュリノーマは中年期を過ぎたフェレットに最も一般的に認められる腫瘍性疾患の一つです。膵臓のβ細胞の過形成や腫瘍化によってインシュリンの分泌が過剰になり、低血糖を生じます。実際に臨床上認められる症状としては元気消失、慢性的衰弱、食欲不振、体重減少、異常行動(普段はおとなしいのに飼い主に噛みつく、ボーっとしているなど)などが見られます。インシュリノーマの仮診断には以下の「ウィップルの三徴」が用いられています。①低血糖に関連した症状がある(痙攣、昏睡、錯乱、頻脈、低体温、不安、過敏など)②空腹時低血糖がある(<60㎎/dl)③給餌およびグルコース投与で神経症状が軽減する。これに当てはまればインシュリノーマの可能性が高いと考えられます。確定診断をするには開腹手術による生検が必要になりますが、そこまでする体力がない場合などにはオプションの検査として血中インシュリン濃度の測定なども診断の助けになります。
インシュリノーマの治療は、まずは食事療法です。高たんぱくのフードを一日6回以上に分けて与えます。糖類は腸での吸収が早いので血糖値が急激に上昇し、これによりインシュリンの分泌が刺激されるので低血糖に陥ります。ですので、糖衣のサプリメントなども与えるのは避けた方が良いです。食事療法だけで血糖値のコントロールが出来ない場合は、肝臓での糖新生を促進するグルココルチコイドやインシュリンの分泌を抑制する働きのあるジアゾキシドの投与を開始します。
インシュリノーマは外科手術も適用となりますが、手術には熟練が必用であり、肉眼的に確認できないような微小な腫瘍が潜在していることから、根治的な治療法にはなりません。しかし、インシュリン分泌の過剰な組織を減らすことになるので症状の軽減や、内科療法でコントロールしやすくなります。また、平均生存期間も、内科療法だけの場合219日ですが、外科手術と内科療法を併用した場合462日であると報告されています。
インシュリノーマは根治の大変難しい病気ですが、早期発見と積極的な治療により幸福な余生を過ごせるはずです。
M.M.